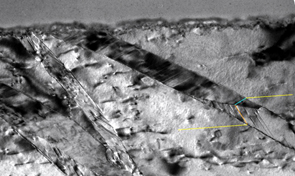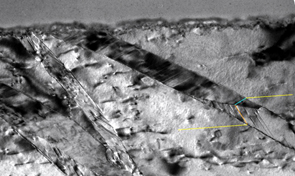● 多結晶マグネシウム合金における室温変形機構の解明 ●
Key word
: 軽量構造材料、自動車、双晶変形
マグネシウム合金は次世代軽量構造材料として現在注目を集めています。 単位体積当りの重さで比較すると、鋼:7.9、アルミニウム:2.7、マグネシウム:1.8となり、マグネシウムは現在頻繁に用いられているアルミニウムよりも約30%も軽い金属なのです。 また、ただ軽いだけではなく強度の点おいてもマグネシウムは優れています。 いくら軽い金属であっても強度が低ければより大きな部品を作ることになり、結局部品自体の重さはそれほど軽量にはなりません。 材料固有の強度を意味する「比強度」(強度を質量で割った数値)でも、マグネシウム合金は従来の金属より優れており、マグネシウム合金を用いることにより製品の強度を維持したまま、軽量化を実現することができます。
左上の図は当研究室で所有しているノートパソコンですが、この製品の天板はマグネシウムでできています。 最近の小型電子機器は軽量なものが多くなっていますが、このようなノートパソコン・携帯電話やデジカメの筐体にマグネシウムが使用されています。
マグネシウム合金の実用化は進められていますが、技術的な課題は未だ多くあるのが現状です。 その課題のひとつに加工性の悪さがあります。 マグネシウム合金はアルミニウムなどに比べて伸展性が乏しく、成型加工の際に割れやすいと言われています。 これはマグネシウムの特徴の1つである変形異方性というものが影響しているためです。 変形異方性とは、結晶の方向によって変形の特性が異なることを言い、簡単に言うと単結晶体を縦方向と横方向に変形させる時では強度や破断伸びが異なることを言います。 一般的にはこの変形異方性が変形を不均一にさせ、加工性を悪化させていると考えられています。 現状のマグネシウム製品が比較的小さいものに限られているのは、変形加工が難しいために主に溶融加工で作られているからです。 マグネシウム合金をより大きな製品に安く供給するためには、変形加工性を向上させる必要があります。
多結晶マグネシウム合金に圧延加工・押出加工・ECAP加工などを行うと結晶の配向が変わり、それぞれの加工に特有な集合組織を生じます。 例えば、圧延加工であれば板面と六方晶底面{0002}結晶面が平行に近くなるような集合組織となります。 マグネシウム合金は変形異方性が顕著なため、そのような配向の違いが変形挙動に大きな影響を及ぼします。 このような配向による変形挙動の違いが、どのような原理で生じるのかを、明らかにしていくことも当研究室の取り組みのひとつです。
また、マグネシウム合金において未解明な点の多い変形双晶のについての研究もあります。 マグネシウム合金は変形にともなって変形双晶が形成されますが、変形特性に与える双晶形成の影響についてはこれまで明確に理解されていませんでした。 当研究室の取り組みでは二重双晶と呼ばれるある種の変形双晶が局所的な変形をもたらし、破断(破壊)の起点として影響を及ぼしているという知見が得られています。 この他にも変形機構を理解するための様々な研究が行われています。
論文へのリンク 当研究室ではマグネシウム合金の加工性向上に役立つ新たな原理・知見を得ることを目的として、マグネシウム合金の変形機構について研究しています。 変形機構とは(非専門的な言い方をすると)どのようなメカニズムでマグネシウムが変形していくのかという意味になります。
図.変形双晶の断面組織写真
双晶の種類によっては
局所変形をもたらし破断に影響を及ぼす